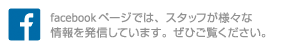中国の原子力発電所での事故の報道、ドキッとしましたね。事故報道のあった台山(Taishan)原発は、香港の南西130km。付近の大気が貿易風や偏西風と合わさって日本列島にも流れてくることなどを連想、対岸の火事ではすまないだろうなあと心配性の筆者はドキッとしたわけです。
事故報道から4、5日が経って、日本のモニタリングポストで異常な数値はあらわれていないというニュースを見てひとまず胸をなでおろしました。とはいえ、そのモニタリングポストとやら、どこで測定しているのかとこれまた心配になり、調べて見ました。
正式には「緊急時環境線量情報予測システム」。長いですね、漢字11にカタカナ4、合計15文字。略してSPEEDI。国内の原子力発電所の周辺に設置してあるんですね。当然、鹿児島では川内原発(せんだいげんぱつ、薩摩川内市)周辺にあり、SACLA源泉の大隅半島にはないようです。
設置図をみてあらためて、この地震大国にこれほどたくさんの原発。まるで闇に潜む悪魔が、日本人の逃げ場がないように散りばめたんじゃないかと思われるほど。事故が起こらないことを祈るばかりですね。

出先であまり話したことのない人から「傘は何色ですか?」と唐突に聞かれました。「傘の色ですか?」と聞き返すと「ほら、傘の色で景色が違って見えるじゃないですか」とたたみかけられました。
ん?色付きの傘がフィルターになって見え方が変わる、それとも道行く人の傘の色で景色がちがって見える?
もたつきながら「黒い傘ですが」とようやく答えましたが、その人は問いかけなどなかったかのように私の返事をスルーして「それじゃ、また」と立ち去りました。
私と年齢差30年以上はあるにちがいない若い女性でした。単なるコミュニケーションギャップ?それともやはりジェネレーションギャップ?しばらくもやもや感ただよう梅雨空の日の出来事でした。
さほど暑くなくても湿度の高い日々、気付かないうちに熱中症になることもあります。この時期には意識して水分補給を。

梅雨空のこの時期になると、肌に赤いぶつぶつができたこどもが小児科には増えるそうです。時期が時期だけに、食あたりや食べ物アレルギーを心配するお母さんたち。でも皮膚の赤い発疹だけだと、食べ物アレルギーが原因のケースはさほど多くないとのこと。
発疹の原因は、ツバキやサザンカの葉につく毛虫、チャドクガの幼虫が原因の場合が多いのだそうです。毛虫の毛に毒があり、毛が肌に刺さることはないものの、毛虫のついた木に触れただけでかぶれたり、発疹ができたりするらしいですね。
そういえば、筆者も何年か前のこの時期、葉桜の緑が目に清々しい好天に誘われ、自転車で桜の枝の下をさっそうと走り抜けたあと、いつのまにかおでこのあたりが猛烈に痒くなり、帰宅した頃にはブツブツだらけの顔を鏡で見た覚えがあります。枝の下でゆらゆらしていたクモの糸のようなものにふれた気がしたので調べてみると、桜の木にはマイマイガという蛾の幼虫がついて、糸を吐いて枝にぶら下がっているそうです。それに触れてしまったのです。かゆみ、ぶつぶつとも強烈。存在感はんぱない毛虫ちゃんの思い出。
きれいな花には棘だけじゃない、毛虫もいる!、、、もちろんヤブ蚊やダニなど、公園で散歩や戸外での仕事の邪魔者たちは他にもいます、木々の種類や、虫たちにも目を配ってお気をつけください。もちろん、飲み水もお忘れなく。日差しが強くなくても湿度が高い日は熱中症も要注意です。

温泉の中には「炭酸泉」といわれる種類の温泉があるのはよく知られているところ。海外、とくにドイツの炭酸泉、まるでプールのような炭酸泉に水着で入っているイメージが浮かぶかもしれません。日本はというと、大分県に炭酸泉が多いそうですね。自然と一体になったかのような建築で知られる藤森照信さんの手になる温泉宿など、コロナ禍が明けたら筆者も行ってみたいところの筆頭。
炭酸泉は、浴用では血行が良くなるなどの健康増進効果が認められていますが、飲用としても健康にいいのは、言わずもがな。残念ながらさくらじまのやさしい水SACLAは、炭酸ガスは含んでいません。常温での飲用をおすすめしているSACLAですが、蒸し暑さが増してくると、SACLAの炭酸水もいいかも、などど夢想してしまいます。
でもまあ、夢想は夢想のままにしておきましょう。暑いからといって、くれぐれも冷たい水のがぶ飲みはなさりませんよう!水分補給は、水がいちばん。常温がおすすめです。

何年か前にこのSACLAのホームページをリニューアルしようとして、うっかり過去のブログをすべて飛ばしてしまうという、とんでもないミスをやらかしました。
そこから気を取り直して、なんとか新装ホームページはオープンまでこぎつけているのですが、未だになくした過去のブログに未練タラタラ、、、。
そんな思い出ブログといっしょになくした写真がじつは残っていることにいまごろになって気付きました。
掘り出しもの写真から、とりあえず一枚。新型コロナウィルスの世の中になってから一般人には、どこか遠くなってしまった旅らしい旅。自分が撮った旅の写真さえ、幻のような気がします。
ヨーロッパ(写真はパリ)のレストラン、やっぱりワイン。おともの水はガス入り。

昨日、3月30日は”東京、10年ぶりに黄砂”のニュースが全国ニュースとして報じられましたね。鹿児島では、春先の風物詩。鹿児島湾をはさんで対岸がかすむ光景を目にすると、ああ黄砂だなぁ、春だなぁ、と感じるわけですね。
大陸から風に乗ってくるので、当然鹿児島に限られるわけではなくて、九州全域、だいたい同じ。ということからでしょうが、九州大学が黄砂の観測や、予測、影響を研究しています。「土壌生ダスト(黄砂)の予想分布」というウェブサイトでは前日から3日間の予想動画をみることができます。それによると、今回の黄砂、昨日は沖縄を除く本土、列島全体を覆いつくしていましたが、これほどのことはめったにないので、全国ニュースになったということですね。
明日4月1日になると、大半が日本列島の南部の太平洋上に移動して、鹿児島の南部にまだかすかに残る。鹿児島は、かくしていつもの風物詩としての黄砂、というわけです。