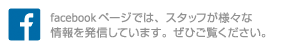さくらじまのやさしい水、SACLAの源泉がある垂水市から見える桜島は、南側斜面です。桜島の写真や、また多くの画家たちが描いてきた風景画もほとんどが南側から見える姿。このブログの写真は、真北からの桜島遠望です。いつも逆光になってしまう北側。写真家、画家泣かせなのです。
さて、桜島。錦江湾の奥まったところの湾の真ん中にあります。わずか百年ほど前までは、その名のとおり「島」だったのに、1903年(大正3年)の大噴火で1ヶ月の間に「島」ではなくなりました。噴出した大量の溶岩で東側の大隅半島と陸続きになりました。
地元では、ほとんどの人が錦江湾と呼ぶこの海。どうやら社会科的には鹿児島湾が正しい?ようですが、錦江湾の名前の由来はじつのところどうなのか。調べがついたらここにちゃんと書きます。
鹿児島市の近郊に吉野公園というところがあります。春、花が満開の時期に青春を謳歌したほの甘い思い出。謳歌は、言い過ぎですが、同級生たちと遠出して愛でた、というだけなのに、なぜかくっきりとした思い出になっています。
ところでソメイヨシノの寿命の話題が少し前には賑やかでしたが、このところあまり耳にしなくなってきました。いま、どうなってるのでしょうね。
パステルピンクの華奢な外見と散り際の良さをウリに世間の同情をよんだのか?とあさましい思いもよぎりますが、案外、ヒトがかしましく言うほどには華奢でもないのではと、桜の生命力を期待したいSACLA社ではあります。
日本有数の活火山、桜島の名前の由来はいろいろとあるようです。ブログ子としては、ウィキで見かけた木花咲耶姫命を由来とするのがいいなあと思います。古事記など、神話の時代と言われているものの、最近は、南九州でも古代に属する地層、というより、縄文時代、それも旧石器時代に遡るような地層にいたる発掘がおこなわれて、その世界ではアツい状況のようです。桜島の名前の由来も、それぐらいの時間尺度で考えられたら嬉しい。

桜@皇居
命名といえば、SACLA。ご存知のことと思いますが、この名前でググると、兵庫県にある理研の巨大な研究施設がトップに出てきます。でも、生まれたのはほとんど同じ時期でした。理研の、東京で開かれた一般向けの最初のシンポジウムにブログ子も行ったほど。また、イタリアには、同じ名前の食品メーカーもあるんです。
イタリアのSACLA社のことは調べて知っていましたが、理研の研究施設の名前とおんなじだったのは、びっくり。シンポジウムで名刺交換した研究者の方にSACLAさくらじまのやさしい水をお贈りしたものの、なしのつぶてで、若かりし頃の吉野公園のほの甘い感傷を久々に思い起こさせていただきました。

東京工業大学の地球生命研究所のチームがSACLA源泉で採取した温泉水を分析して、天然の水素が検出されたことについて、じつはいまだになぜ、水素が含まれているのかわかっていません。
地球生命研究所が日本国内の温泉水の調査をしたのは、ウェブサイトの記述や調査に当たった当時の研究者の発言によれば、文字どおり生命の起源を地球内部の火山活動に求めていたのではということがうかがわれます。
その後、弊社から新たな試料を提供して、関連の別の国立研究機関での分析も行われました。これらの分析結果や、データは、口外することを控えてほしいと言われてきました。
ただし、その分析データや画像データは弊社に開示されました。いつか、許されれば公開したいと思っています。
このブログは「水素検出の不思議」などとおおげさなタイトルをつけましたが、それは、地下800mのSACLA源泉の地層に由来します。そこは凝灰岩層になっています。
一般的なミネラルウォーターのイメージは、ミネラルウォーター業界発祥の地、例えばアルプス山脈の山頂に降った雨が、人間活動に汚染されていない岩石層を滲み降りてくるうちに、
ミネラルを含んだ清冽で無垢な飲料水になっているというものです。このイメージは、いま日本国内のミネラルウォーター業界のマーケティングでも同じように採用されています。
ところが、地下から、それも海抜ゼロメートルの地点の地下から湧出してくるミネラルウォーターなどというものは、だれもイメージしてこなかったのです。
東京工業大学地球生命研究所チームは、まったく別の視点、火山活動と生命の起源という視点からこの源泉にアクセスしてきました。さくらじまのやさしい水に、どんな謎があるのか。水素検出の不思議は、次回?ブログでご紹介します。
水素水については、説明の必要もないほど様々な情報、広告があふれています。そのほぼすべてが人工的に水素を充填した“加工水”です。ちょっと乱暴ですが、簡単に言えば“水素ガスを注入した水”。
でも天然水素となるとあまり情報がありません。それもそのはず。ナチュラルミネラルウォーターに天然水素が含まれているというのは、とても希少な“現象”なのです。
SACLAの源泉に天然水素が含まれていることは、国立東京工業大学の研究チームが発見しました。その含有量は0.55ppm。含有量としては微量ですが、この分析結果に研究チームも驚いたとのこと。なぜ天然水素が検出されたのか、予測外の事象だったようです。
SACLAには、ペットボトル入りがありません。温泉水ナチュラルミネラルウォーター「さくらじまのやさしい水」は、すべてBIB(バッグインボックス、Bag in Box)といわれる容器入りです。
SACLAは、天然水素含有、酸化還元電位-390mVのすぐれた抗酸化力のある水です。ところが水素も酸化還元電位も、光や空気(酸素)には弱い。ペットボトルのような透明でむきだしの容器に入れたのでは、すぐに抗酸化力が弱まってしまいます。そこでBIB容器の出番。
BIBは、ダンボール製の外箱の内側にポリエチレン製のバッグが収まっています。このバッグの中に水が入っているので、光は外箱によって遮断されて光による酸化は防げます。酸化のもうひとつの大敵は空気(酸素)。内側のバッグは、空気を遮断するためにポリエチレン素材を二重にして空気による酸化を防いでいるのです。
SACLAスタッフが視察した愛媛県にあるバッグの製造工場の製造工程では、不良品が混じらないように厳密な管理がなされていました。柔らかなプラスチック製のバッグ、小さなピンホールがあるだけで不良品になるのです。日本のものづくりの細かな気遣いが実感されます。
余談ですが、ワイン好きのヘビーユーザーの中にはBIBがおなじみの方もあるかもしれません。3〜5リットルの大容量の輸入ワイン。こうしたワインのBIB容器は、内部のバッグが銀色、これはポリエチレン素材をアルミ蒸着で加工したもの。ワインにとっても酸化は大敵なのです。
そこでアルミニュームの層で透明なポリエチレンを覆うことで光と空気の遮断力を高め、より抗酸化力の強いパッケージにしているのだそうです。
ワインと同じように、ミネラルウォーターのBIBのバッグもアルミ蒸着でもっと抗酸化力が高まるのでは?と期待が高まりますね。
ところが上記の愛媛県の製造工場で聞いたところでは、通常のバッグ製造方法は熱圧着なのにアルミのバッグは接着剤が必要なので水の容器には使えないのだそうです。ワインなどの酒類や調味料にはそれ自体の強い香りがあるので接着剤の匂いに消費者が気づくことはない。
でも、水はどんなものでも溶かす(金属でも岩でも!)最強の溶剤なので、わずかな異物の匂い成分でも溶かし込んでしまうため、接着剤を使うとたちどころにその異臭が水から感じられてしまうというのです。
でも今後、日本のものづくり力で優れた水質の温泉水ナチュラルミネラルウォーターの容器として、よりすぐれた容器が出現するようにSACLAとしても容器メーカーを応援していきます。
温泉学の専門家の松田忠徳博士(札幌国際大学観光学部 前教授)は、かつて連載していた日経新聞の「列島縦断2500湯」でSACLA源泉について次のように紹介しています。
「垂水温泉は凄かった」という前置きにつづけて、「まろやかな湯で肌触りも抜群。シルクの感触といったらいいだろうか。」と。
ここで松田博士が記す“シルクの感触”は、この源泉がpH9.8のアルカリ性であることによってもたらされています。いっぽう、この源泉は硬度1.4という超軟水。マグネシウムやカルシウムなどのミネラル量の少ない水です。硬度が低いほど水の“まろやかさ”が増します。ここでいう“まろやかさ”は、肌触りではなく、味覚のこと。
すると、このブログのタイトル“シルクのようなまろやかさ”どちらのことを言っているの?とわからなくなりそうですね。
そこで水質の特性をそれぞれ探っていくと、たしかに肌触りと味覚の両方の特質を示しているのだなと、少し理屈っぽいひもときになってしまいます。
でも、SACLAスタッフは、この両方の特質が別々のものではないような錯覚を覚えるのです。それは、SACLAをくちに含んだときの感覚。味のまろやかさと水そのもののやわらかい感触が同時に口中で感じ取られ、それがSACLA独特の美味しさを生み出している秘密ではないかと。
“シルクのようなまろやかさ”はSACLAの美味しさをお伝えしたいというスタッフの願いでもあるのです。